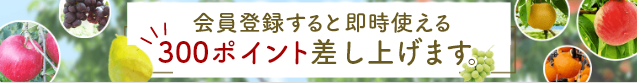南信州の特産物「市田柿」とは?栽培方法やおすすめ絶品干し柿を紹介

もっちりとした食感と強い甘みが特徴の干し柿として、全国で広く名が知れわたっている市田柿。
皆さんはその栽培方法や、干し柿への加工工程をご存じですか?
市田柿が誕生するまでの流れを知ると、より味わい深く食べられるはず。
今回は市田柿の歴史や栽培方法、そして実際にCOCORO FARMで行っている製造方法の内容について、情報を詳しくお伝えします。
南信州の特産品「市田柿」とは?

まずは市田柿について学んでいきましょう。
市田柿とは渋柿を乾燥させて作った加工食品のことです。
乾燥させるという工程から、ドライフルーツの一種に分類されます。
ドライフルーツはりんごやパイナップルなどいろいろな農産物を使って作られますが、その理由をご存じですか?
実はドライフルーツに加工することで、さまざまなメリットがあるのです。
【ドライフルーツのメリット】
- 長期間の保存が可能
- 栄養が豊富
- 腹持ちが良い
生のままでも栄養価が高いフルーツ。
乾燥させることで果実から水分が抜けて、その粒に栄養がぎゅっと詰まります。
少量でも効率的に栄養摂取できるうえに、乾燥することで噛み応えがアップして腹持ちが良くなることから、ダイエット中のおやつとしても人気が高い食品です。
市田柿の栽培は地域限定
市田柿は生の柿を干して作りますが、どの柿を使っても良いというわけではありません。
特産品である市田柿を名乗るためには、長野県にある特定地域で栽培された柿を使用する必要があります。
特定地域に指定されているのは以下の地域です。
- 飯田市
- 下伊那郡
- 上伊那郡飯島町・中川村
この限られた地域で栽培された柿は、干し柿同様に「市田柿」と呼ばれています。
この市田柿(青果)を使って作られる干し柿だけが、特産の市田柿を名乗ることができるのです。
実はそのままでは食べられない市田柿
特定の地域で大切に育てられる市田柿(青果)。
生のままでも美味しく食べられるのでは?と思われることもしばしばですが、市田柿は「渋柿」です。
生のままでは渋くて食べられません。
ではなぜ、干し柿にあえて渋柿を使用するのでしょうか?
甘柿と渋柿、糖度が高いのはどっち?
甘柿の平均糖度は16度前後といわれています。
一方の渋柿は20度前後であり、甘柿よりも高糖度なのです。
しかし生のまま食べてしまうと、糖度を感じるよりも先に渋みを感じてしまいます。
そこで行われるのが「渋抜き」です。
渋柿の渋みは「タンニン」という成分が原因となっています。
このタンニンは水溶性で、柿の中に水分があると溶けだして苦みを生み出します。
そこで柿から水分を取り除き、タンニンが溶けださないようにすると、渋みを感じなくなるのです。
渋みを感じなくなったことで、元々含まれている甘みをしっかりと感じられるようになります。
市田柿の栽培方法

ここからは市田柿がどのように栽培されているか、その過程について学んでいきましょう。
市田柿(干し柿)が販売されるのは冬頃、おおむね12月前後からですが、実はほぼ1年をかけて栽培~加工を行っているのです。
おおよその年間スケジュールにそって紹介します。
2月・剪定作業
2月頃になると干し柿の加工・出荷作業も落ち着いてきます。
ちょうどそのころから枝の状態を見極め、剪定作業が始まるのです。
美味しい市田柿を栽培するために重要なのは、元気な枝と疲れた枝を見極めて剪定していくこと。
そのうえで、去年の剪定状況や2・3年先の予測も行いながら、製造量に影響がないように調整していきます。
剪定作業を終えた柿の木は、4月頃になると緑の葉が芽吹きます。
美しい緑の葉っぱが芽吹いたあとの5月には、真っ白な柿の花が開花。
花が落ちてしばらく経過した6月頃、小さな緑の実がなり始めるのです。
7月~8月・摘果作業
実が少しずつ大きくなってきた夏頃、摘果作業が行われます。
その年の降雨量や日照時間、気温によって、柿の成長はまちまちです。
成長度合いを確認しながら、1つの枝に残す柿の実を選びます。
この作業を行うことで、大きさや糖度がある程度そろった柿を収穫できるようになるのです。
10月・収穫作業
柿の実の成熟状況を見極めながら収穫を行います。
ヘタの周りまでしっかりとオレンジに色づいた柿から収穫を行い、順次干し柿への加工作業に移っていくのです。
市田柿が美味しい干し柿になるまでの工程

こうして収穫された市田柿(青果)は、干し柿へと加工されていきます。
干し柿になるまでには多くの手が必要です。
順番にチェックしていきましょう。
①選果作業
まずは収穫した柿の実を大きさ別に分けていきます。
製造後の干し柿はサイズや形などで等級が分けられるため、重要な作業です。
またこの段階で、改めてしっかりと熟しているか、傷んでいないかを注意して確認します。
干し柿に向かない個体は取り除き、次の工程へ。
②皮剥き
選別した柿の皮を剥いていきます。
皮剥きには専用の機械を利用し、1日に約10,000個の柿の皮剥きを行います。
昔は手で皮を剥いていましたが、包丁を使った皮剥きでは1日に約450個程度が限界で、大量に生産することができません。
COCORO FARMで生産する個数をすべて剥くには、機械を使っても約1週間ほどかかります。
③硫黄燻蒸
皮剥きを終えた柿に、硫黄燻蒸を行います。
硫黄燻蒸は、少量の硫黄を燃やして生まれる煙で燻すことで、市田柿の製造に欠かせない作業です。
硫黄燻蒸を行うことで「変色予防」「カビ抑制」「乾燥促進」などの効果が生まれます。
製造過程で硫黄燻蒸を行った商品の場合、パッケージに「硫黄」と記載があるのでチェックしてみましょう。
人体に影響のない方法・分量を使用していますので、ご安心ください。
④干し作業
作業はいよいよ干し工程へ。
柿のヘタについているホゾと呼ばれる枝を、専用の器具に引っ掛けて紐でのれん状に吊るします。
外にのれん干ししている姿も見かけますが、これはすべて家庭用の干し柿です。
商品として加工する場合、衛生面から屋外でののれん干しは禁止されているため、基本的にはビニールハウスが作業場となっています。
⑤ホゾ切り
一定期間のれん干しを行ったあとは、のれんから柿を外し、ホゾ切りを行います。
ホゾはのれん干しに欠かせない部分ですが、このあとの工程では柿を傷つけてしまう原因となるため、1個ずつ切り落としていくのです。
1個ずつ行うため大変な労力なのですが、この工程は機械化が難しく、すべて手作業で行います。
はさみを使って1日に何千個もカットしていくため、とても大変な作業です。
⑥揉みだし作業
ホゾ切りした柿はコンテナに広げ、天日干しと交互に「揉みだし」作業を行います。
揉みだしとは、柿を揉むことで表面に細かな傷をつけて、糖を含んだ水分を表面に排出させること。
COCORO FARMでは、ドラムの中に柿を入れて回して揉みだします。
回し終わった柿は再びコンテナに入れて天日干しへ。
揉み出しと乾燥を繰り返すことで、柿の表面に真っ白い粉が表れ始めます。
この粉は「柿霜」といって、柿の中にある糖分が水分蒸発と共に表面に現れたものです。
市田柿が持つ、上品でありながら強い甘みの象徴でもあります。
⑦梱包作業
しっかりと柿霜が表れたら、梱包作業に移ります。
まずは市田柿を重量別に分類し、規格別に分けて箱に詰めていくのです。
特に、贈答品用の商品「白箱」は個包装された商品です。
1個ずつ人の手で検品しながら、個包装袋に脱酸素剤と一緒に封入していきます。
そのあとオリジナルの化粧箱に詰めて完成です。
【COCORO FARM】南信州の市田柿を全国にお届け!

今年に製造する市田柿の注文については、COCORO FARMのオンライン通販サイトにて受付をしています。
その中から本日は先ほど紹介した「白箱」のリンクをピックアップ。
市田柿の証ともいえる地理的表示制度認定「GIマーク」を掲載しているため、贈答品として安心してお買い物いただけます。
特秀品とランク付けされた市田柿を、10個入り、20個入りでご用意。
価格含め在庫の状況や送料、発送、支払い方法といった商品に関する疑問・質問があれば、以下のページよりご確認ください。
また、以下のページよりCOCORO FARMで販売されている市田柿を一覧で確認できます。
南信州の絶品市田柿をお家で気軽に楽しもう♪

市田柿は信州の飯田、上伊那の一部地域、下伊那という特定の場所だけで栽培された渋柿を使って、1年を通して手間暇かけて栽培・製造を行います。
どの工程に携わる人でも「美味しい市田柿を全国のお客様に届けたい!」という思いは一緒。
皆さんの笑顔を思いながら大切に作業した、ぜひ味わっていただきたいと思っています。
今年の冬はGIマークが表示されたブランド干し柿の市田柿を、温かい部屋でゆっくりと楽しんでみませんか?
オンラインストアで皆さんのご注文をお待ちしています。