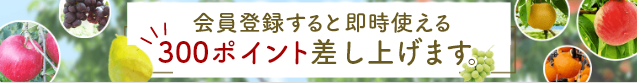和紅茶とは?紅茶との違いと楽しみ方について解説します

日中の気候が暖かくなってきた春先は、お出かけにピッタリな季節です。
最近では、外出の際に節約も兼ねて水筒を持参する人も多いと思います。
今年はいつもの紅茶と一味違う「和紅茶」を水筒に入れて、春のお出かけをしてみませんか?
今回は、爽やかな香りとほのかな甘みが楽しめる「和紅茶」について解説します。
和紅茶とは?

皆さんは和紅茶という名前を聞いてどんな印象を持ちましたか?
「和」という言葉が付く通り、日本にまつわる紅茶だと想像する人も多いかもしれません。
その通り、日本国内で茶葉の栽培から製造加工までを行った国産の紅茶のことを指します。
和紅茶の歴史
日本に紅茶が広まり始めたのは今から約170年前、江戸時代の末から明治初期にかけてのことです。
現在の三重県・伊勢で船頭をしていた大黒屋光太夫が、遭難の末にロシア領の島に漂着しました。
紆余曲折を経てエカチェリーナ二世(当時のロシア女帝)のお茶会に招待されたのが、紅茶が日本に伝わるきっかけの一つとされています。
このお茶会はのちに、日本人が初めて正式な茶会に招待された場として認定され、開催日である11月1日を「紅茶の日」に制定されました。
ちょうどこの頃は、海外との交易が盛んになってきた時代でもあり、諸外国との貿易のなかで紅茶が輸入され始めたのも、まさにこの時期です。
製造が盛んになった明治時代
明治に入ったころ、日本でも本格的に紅茶用茶葉の栽培がスタートしました。
当時、紅茶は非常に貴重で高価な交易品であり、海外との取引において重要な品物のひとつでした。
より多くの紅茶を製造するために、政府が奨励政策を行っていたことからも、どれだけ貿易量として重要視されていたかが伺えます。
紅茶製造のための海外視察も積極的に行われていました。
インドや中国といった紅茶栽培が盛んな地域に、多田元吉という人物が派遣されています。
彼は主要な産地で紅茶茶樹の栽培・加工方法を学び、日本にさまざまな技術や知識などを持ち帰りました。
合わせて、アッサムやダージリンなど、今でも紅茶の茶葉としてよく知られる品種を導入しています。
また彼の持ち込んだ技術は、紅茶だけでなく緑茶栽培へも影響を及ぼしました。
紅茶以外にも、煎茶やほうじ茶、抹茶などの他の日本茶も、加工方法の違いにより異なるお茶になります。
彼が紅茶製造のために学んだ栽培技術や道具は、日本茶の栽培に応用され、大量生産や品種改良などにつながっていきました。
多田元吉は当時の日本における茶類栽培の発展に貢献し、日本近代作業発展の基礎を築いた人物として、高く評価されています。
和紅茶の衰退と復活
国内での生産力を拡大させていった日本ですが、昭和に入り第二次世界大戦を経ると、紅茶の輸出品としての価値が低落していきます。
今までのような高い価格で輸出することが難しくなり、さらに1971年(昭和46年)に紅茶の輸入自由化がスタートした影響で、国産紅茶の製茶・流通量は減少していきました。
明治時代から続いてきた国産紅茶の製造が、途切れそうになったのです。
そんな中でも日本産紅茶の歴史を途絶えさせないように、地道に研究や努力を続ける人たちがいました。
そして1995年、ついに「べにふうき」という日本産紅茶用茶葉が誕生しました。
べにふうきは、かつて多田元吉が日本に持ち込んだアッサムを品種改良した「べにほまれ」と、ダージリンを改良して作った「枕Cd86」を掛け合わせて生まれた茶葉です。
こうして明治時代に始まった日本産紅茶の歴史は、平成に入ってその努力が実を結び、和紅茶と呼ばれて親しまれるようになりました。
今ではそのやさしい味わいが紅茶好きの間で広まり、注目を集める存在となっています。
和紅茶の生産地とその特性
和紅茶の生産は日本全国各地で行われていますが、特に有名なのが以下の地域です。
- 静岡県
- 鹿児島県
- 熊本県
- 宮崎県 etc…
- 萎凋…茶葉を乾燥させる
- 揉捻…茶葉をよく揉んで酸化させ、形を整える
- ふるいがけ…ふるいにかけて大小に分け、大は再度揉捻する
- 発酵…湿度や温度を一定に保てる部屋で茶葉を広げ、発酵を促す
- 乾燥…水分量が3%程度になるまで乾燥させる
- ゼラチン…5g
- 和紅茶(抽出済み)…300~400ml※
- 水…大さじ2
- ゼラチンに水を加えふやかしておく
- 抽出したての熱い紅茶に①を入れ、よく混ぜ溶かす
- タッパーなどの容器に入れて粗熱をとり、冷蔵庫で固まるまで冷やす
- タッパーからゼリーを取り出し、一口サイズにカットする
こうしてみると緑茶生産の盛んな静岡や九州地方で、比較的生産量が多いことが分かります。
茶葉の栽培には「降雨量の多さ」「温暖な気候」「昼夜の寒暖差」といった条件が必要です。
インドやスリランカ、中国などの世界的に紅茶の栽培が有名な国々には、これらの気候が揃っているため、質の良い茶葉の栽培が可能となります。
また、国内の主要なお茶の産地も、この条件を満たしている地域が多いです。
和紅茶と紅茶の違い

和紅茶は日本国内で栽培・製造された国産の紅茶であり、紅茶は海外で作られたものを指しています。
ここからはこの2つの紅茶の違いを詳しく比べていきましょう。
製法の違い
紅茶の製造工程はざっくりと「オーソドックス製法」「アン・オーソドックス製法」の2つに分けられます。
和紅茶の場合ほとんどがオーソドックス製法で、海外紅茶の多くは「アン・オーソドックス製法」で作られています。
オーソドックス製法
200年程前から諸外国で使われてきた製法です。
アン・オーソドックス製法(CTC)
海外産紅茶ではアン・オーソドックス製法も頻繁に使われています。
インドのアッサムはこのアン・オーソドックス製法で製造される代表的な品種です。
アン・オーソドックス製法では主に2つの手法が使われますが、今回は一般的なCTC製法について紹介します。
CTCとは紅茶製造に特化した特殊機械のこと。
「Crush(押しつぶす)」「Tear(引き裂く)」「Curl(丸める)」の頭文字をとって名付けられました。
そのため、この工程を経て出来あがった茶葉は、丸い形状で仕上がります。
萎凋した茶葉をこの機械に入れることで、揉捻からふるいがけまでを自動で処理してくれるのが特徴です。
近年では乾燥まで一貫して行えるマシンも登場していて、紅茶製造の効率化に大きな一役を買っています。
味わいの違い
紅茶といえば、特有の渋みやしっかりとしたコクが魅力のひとつではないでしょうか。
一方の和紅茶は海外産と異なり渋みが少ないため、飲むと口の中でほんのり甘みを感じるのが特徴。
これは和紅茶に使われる茶葉が、日本茶用茶葉を品種改良して作られためです。
和紅茶は、砂糖やミルクを入れなくてもほんのりとした甘みがあります。
そのままでも十分に美味しく、お菓子と一緒に楽しんでもカロリーを気にせずに済むのもうれしいポイントです。
香りの違い
海外産紅茶は華やかで強い独特な香りが特徴的です。
一方で和紅茶は、柑橘類のような爽やかな香りを楽しむことができます。
これも味わい同様に、緑茶をルーツとする和紅茶ならではのポイントです。
和紅茶の楽しみ方

国産の茶葉だけを使い、日本国内で製造した和紅茶。
その味わいを最大限に引き出すたために、覚えておきたいポイントを2つ紹介します。
美味しい和紅茶の淹れ方
まずは淹れ方を押さえておきましょう。
美味しい和紅茶を淹れるために大切なのは「計量」「温度調整」「時間管理」です。
計量
茶葉で購入した場合、ティーポットや急須などの茶器に入れる前にしっかりと計量してください。
茶葉の種類によって分量は多少変わりますが、おおむね300mlのお湯に対し茶葉5gほどが目安です。
茶葉のパッケージに推奨量が記載されていれば、そちらに従いましょう。
温度調整
和紅茶が持つ美しい色や豊かな風味、味わいを引き出すためには、お湯の温度調整が大切。
汲みたての水道水をしっかり沸騰するまで沸かし、使用してください。
茶葉によっては沸騰後、温度を落ち着かせた方が良いものもあります。
茶葉の量同様、記載されている温度があればそちらを優先しましょう。
時間管理
ティーポットに茶葉を入れて熱湯を注いだら、成分をしっかり抽出するため蓋をして3~5分蒸らしてください。
短いほど軽く、長いほど濃い味わいの和紅茶に仕上がります。
目安時間が過ぎたら茶葉を取り出すか、ポットの中身をすべてカップに注ぎ入れましょう。
茶葉を入れたままにすると時間経過と共に渋みやえぐみが出てしまうので、注意してください。
和紅茶を活用したレシピ

柑橘類のような爽やかな香りと、ほのかに甘い味わいを活用して、こんなスイーツのレシピはいかがでしょうか?
和紅茶ゼリー
【材料】
※水を多くすると、ゆるめの食感に仕上がります
【作り方】
あえて砂糖などの甘みを一切加えず、ストレートの紅茶で作るゼリーです。
トッピングなしでシンプルに味わうのもおすすめですが、仕上げにミルクやホイップを乗せても美味しいです。
爽やかな香りとまろやかな味わいを堪能してみてください。
甘みが欲しい方はカットしたゼリーに、お好みではちみつやガムシロップをかけてみましょう。
また緑茶のような風味があるので、洋菓子だけでなく和菓子との相性も良いのが和紅茶の魅力。
黒蜜とも相性がよいので、ぜひ試してみてください。
ただし紅茶にはカフェインが含まれているので、食べ過ぎには注意しましょう。
後味爽やかで飲みやすいCOCORO FARMの「有機テアフラビン和紅茶」

現在COCORO FARMのオンラインストアで販売している「有機テアフラビン和紅茶」を紹介します。
その名の通り、農薬類を使わない有機栽培で育てた茶葉を利用し、紅茶に加工しました。
茶葉の栽培から紅茶への加工まで、すべての工程を静岡県の茶園にて一貫して行った、生産者のこだわりがつまった特別な和紅茶です。
また、紅茶には、抗酸化力を持つカテキンやポリフェノールが多く含まれいて、生活習慣病を防ぐ効果が期待されています。
身体に気を使う方や、オーガニック・自然食品に興味がある方へのギフトとしても、人気の高い一品です。
ティーバッグタイプなので、茶器を用意しなくてもお手軽に楽しめます。
詳しい商品案内や、発送方法、配送料など、詳細情報は以下の商品リンクからページ内をご確認ください。
和紅茶と紅茶の近いを知って気分に合わせた一杯を

和紅茶と紅茶は同じ紅茶でありながら、味や香りに違いがあることがお判りいただけたのではないでしょうか。
常飲目的で水筒に入れるなら和紅茶、気分をシャキッとさせたいときは海外産紅茶を…。
それぞれの個性を生かして、気分やシーンに合わせて選んでみるのがおすすめです
紅茶をより楽しむのにおすすめの和紅茶、是非日々の生活にプラスしてみてください。